 |
| 郷土色豊かなお祭り・行事・文化財 |
 |
| 郷土色豊かなお祭り・行事・文化財 |
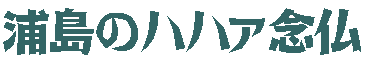 |
| 旧両神村指定無形民族文化財です。 特大の数珠を全員でもち回しながらハハァ~」という節回しの唱文を唱えます。「ハハァ念仏」の起源は明確ではありません。明治のころ盛んに行われており、戦前使っていた鉦には正徳の年号があったといわれますので、江戸時代前期までさかのぼることができるようです。昔は子供連れで出かけ、ごちそうをたべたり、茶飲み話をしたりとコミュニケーションの場にもなっていました。 | ||
| ナムアハヽミダ ハヽイブウナア ハヽマア ハヽイダア ハヽイブー ナアハヽマアイダー ハヽイダー ハヽイブ ブツナア ハヽマアハヽイダー ナアマア ハヽイダーハヽイブ ブツナー ハヽマーヽイダー (7回線返し) アーミンダーサマ ミンダアサマー アーミンダアノーコーライコウデヨ ミンダアサアマー アヽーミンダーサマアンミンダーサーマー (7回線返し) |
ナーハヽアミダー ハヽヽヽヽヽナア ハヽマアハヽイダー ハヽイブーーーナアハヽマー ハヽイダー ナヽヽヽヽミダ ハヽイブー ナーハヽマアハヽイダアナアマー ハヽイダー ハヽイブ ブツナーハヽマー ハヽイダー (7回線返し) アンミンダーノコーライコーデ アンミンダー アミダアサマアンミンダ アミダサマアミンダ ナアイダーナアイダー ナンマイダーナンマイダー (それぞれ2回線返し) | |
 |
 |
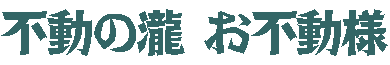 | ||
| 浦島地区六区にあるお不動様には不動明王と弁財天が並んで祀られています。お不動さまは十三仏系の仏さまであり、弁天さまはごぞんじ七福神の一員で神さまです。 神と仏がいっしょなのも不思議ですが、この地域の森林の守り神であることはまちがいありません。 山の神様は滝前の扇の指(オオギノサス)の入り口と村有林外山 (ソトヤマ)と三本栃(サンボントチ)の尾根の三カ所に祀られています。 お祭りは二月の末で、浦島耕地、竹平今袖の人々によっておこなわれます。「オッカドの木」で作った尺二寸の粥掻棒(カユカキボウ)を作って祀り、御嶽神社の宮司によって一年の無事を祈願します。 | ||
 |
 |
 |
 |
 | |||
| 旧両神村指定無形民族文化財です。 両神薄(すすき)竹平の諏訪神社の祭礼に、 五穀豊穣、悪霊退散を祈願して獅子が勇壮に舞い踊ります。 |
秩父小鹿野町のかたくりの里にある毘沙門水……吉田町の西方、上吉田・塚越から合角ダムへと左折し、道なりで4kmあまり。馬上(もうえ)のすぐ手前のところにあります。 水量は豊富で、カルシウム分が多いのが特徴です。やわらかな味わいでとてもおいしいお水です。 標高700mの奥山より延長1800mのパイプをひいてくみ取り口までもってきています。 | |||
 |
 |
 |
 | |
 | ||
| 女人高野として知られたお寺です。 秩父十三仏霊場の一つで阿しゅく如来を祀ってあります。 鎌倉時代末期に開かれ、女人禁制の三峰神社にたいして女子の参詣が許されており「東国の女人高野」といわれています。 深い谷あいに建ち、シャクナゲが境内に茂る禅宗の静かなお寺で、このあたりは紅葉の名所としても知られています。 毎年5月5日に行われる釈迦の降誕を祝う春まつりでは、大般若600巻を転読しする大般若会があります。大般若経が大勢の僧侶により一斉にパラパラと弧を描いて舞う様子は見物です。当日は千手観音のご開帳もあります。 また太陽寺は鎌倉武士の典型として吾妻鏡や歌舞伎、浄瑠璃などにも登場する畠山重忠と縁が深く、太陽寺の阿弥陀三尊は畠山重忠の守本尊であり、鎗一本は重忠の手鎗といわれています。 | ||
 |
 |
 |
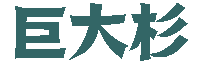 |
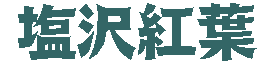 | |||
| 江戸時代の杉という意味で鎌倉杉と呼ばれています。江戸時代の中期ごろまではここに日向大谷集落があり、鎮守に諏訪大明神を祀り、諏訪神社の御神木とされていました。 日向大谷集落は修験道の山である両神山の里宮として重要な位置にありました。したがって鎌倉杉は修験活動や両神神社などと密接な関係があるとされています。 登山口から徒歩約20分/根廻り6.64m/幹廻り4.79m/樹高25m |
同じく両神にある巨木、塩沢のヤマモミジ。両神薄塩沢の山林にあり、林道から徒歩約10分のところにあります。 根廻り5.15m/幹廻り3.23m/樹高13m | |||
 |
 |
 |
 | |
| ウ~ン やはりデカイ! 何百年の風雪に耐え、なお緑の葉を力強く茂らせているさまは神々しいモノがあります。 | ||||